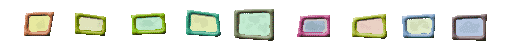
小説 京の嵐
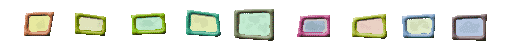
小説 京の嵐

 京 の 嵐
《その一》
作・絵:柳田 通(医学部Ⅲ年) 京 の 嵐
《その一》
作・絵:柳田 通(医学部Ⅲ年)NHKで『新選組』が放映された事があります。私も、今から30年以上も前に、医学部在籍中『新選組』に題材を取って(子母澤 寛「新選組始末期」等も参考)、短編小説『京の嵐』を書いた事がありました。“或る人に読んで貰えれば”と考えた事がきっかけの様な所でしたが、大学新聞に寄稿したものです。連載が長期化しそうになり、編集部から、 「後がつかえているので、程々にして欲しい」と注文を付けられ、後半はかなり内容を詰めた文章になってしまったのを覚えています。 私も小説家を夢見た事もありましたが、小説を書くには経験がものをいう部分もある様な気がしまして、私にはとても小説など書けないと諦めてしまいました。でも、一気に書いた自分の小説をこうして今読み返してみて、まあ能くもこの様な小説を書いたものだと、 当時を振り返って感無量の感じがしています。 お恥ずかしい文章ですが、当院のホームページに載せました。「四話完結」で順次追加して行きます。お時間でも御座いましたら、是非お読み下さい。感想文も御座いましたら、是非お寄せ下さい。 (復刻に際して、極一部手直しした部分があります) (一) 旅立ち 藤枝新一郎が京都に着いたのは文久三年九月十日である。江戸を発って以来半月が過ぎていた。長崎まではこれから二十日は かかるであろう。別に急ぐ旅でもなかった。初めて見る京の都は、江戸の風情とはまるで違い、全てが長閑に見えた。 「二〜三日留まって旅の疲れでも癒そう」 と、その時新一郎が思ったのも無理からぬ事であった。江戸しか知らない新一郎にとって、京はあこがれの都であったし、こうして見る物、聞く物すべてが千年の歴史の響きをもっている様に思えたからである。 人の運命などと言うものは、いつどうなるものか計り知れない所がある。この時の新一郎がそうであった。もし、新一郎がこのまま 京を通り過ぎたなら、長崎のオランダ医学を学んで、父玄以の後を継いでいたであろう。 清閑寺、清水寺を訪れての帰り道、五条大橋に差し掛かった。鴨川の水は澄みきって、東山の木々の紅葉と相まって、一幅の絵の様であった。いよいよ明日は長崎へ出発である。名残は尽きない。『−−行く河の流れは絶えずして−−』と書いたのは、鴨長明だったろうか。京の旅情が心地良い。 と、その時、背後に人の駆けてくる足音を聞いた。京に知っている者が誰一人いない新一郎は、気にも留めなかった。河の水面に映る景色が揺らいでいる。が、それも束の間、するどい殺気を一瞬感じた時、既に新一郎の刀は鞘走っていた。それは、まさしく無の 境地の中への侵入者に対する自然の抜刀に過ぎなかった。五感の為せる筋肉の反射と云っても良いかも知れない。だから、新一郎は一体何事が起こったのかまだ分からないでいた。方丈記の一節が続いている。『−−よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとどまる例し無し−−』 だんだら模様の白装束の武士が血を吹いて倒れた。新一郎は、初めて、然もかくも簡単に人を切った事が信じられなかった。思わず駆け寄って傷口を見た。先祖代々の医者の血が通っていたのかも知れない。左の肋軟骨を切り下ろし、右下腹部まで斜めに傷口が開き、心の臓はかすかに拍動を続けているに過ぎない。手の施しようがなかった。あふれ出る鮮血は白地の羽織を真赤に濡らし、 それでも足りずに流れ落ちて地面に吸い込まれていく。新一郎の全身が総毛立った。血を見る事には慣れている筈であったが、今回は血の量が比較にならぬ程多かった。しかも、自分が斬ったのである。そして、もう相手の助かる見込みはまるでない。新一郎の頭から血の気が引いた。油汗がにじんで、秋風に冷えていくのを感じた時、新一郎は死体を抱えたままその場に気を失って倒れてしまった。 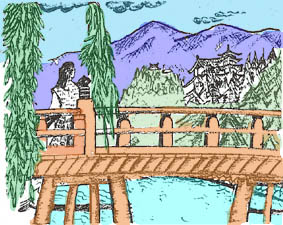 (二) 新選組 「あれの居合いは実に見事でした。死んだ橋田君は可哀想だったが、相手を確かめもせずに斬りつけたんだからまるきり無茶だよ」 「ほほう、総司がそう言うんじゃ、どうやら本物らしいな。どうだ、何とか工夫して入隊させる訳には行かぬか。人手が欲しい」 「おや、土方さんらしからぬお言葉ですな。生国や素性は確かめないのですか」 「こいつ」 「いや、分かっています。あれは江戸でしょう」 「わしもそう思う」 新一郎は沖田総司に活を入れられ、意識を回復した。そして、沖田や、斬った相手が噂に聞く新選組と知って、事の重大さに改めて前途のけわしさを思った。 新一郎とて今の動乱を知らない訳ではない。江戸でも、桜田門外の変や坂下門外の変では、老中でさえ暗殺され失墜させられている。物価の暴騰に庶民はあえぎ、異人の来航騒ぎも知っている。しかし、これまで幕府の膝元で暮らしてきた惰性が、新一郎に事態がこれ程切迫している事を認識させないでいた。京でも、この二日ばかり、表面は平静な所ばかりであった。京の人に、“ここは戦場だ”と聞かされてもピンとは来なかった。だが、今こうして新選組が長州浪人を追って、しかも自分を人違いして斬りつけてきたのだ。 歴史の流れが自分の意志とは無関係に動き出しているのを感じた。 徳川幕府下では、御用医師は士分扱いである。新一郎は、子供心に侍であるという自負があったので、町道場に通う事を親に許して貰った。道場主は、平山勝斎という北辰一刀流の流れを組む常州浪人である。負けず嫌いの新一郎は、それなりに腕を上げた。 或る日、新一郎は勝斎に呼ばれ、庭に出向くと濡れ縁に坐らされた。庭には竹が突き立てられ、その先端には紐が張られて竹は 半弓状に曲げられている。その紐の端に蝋燭が立てられていた。半弓のしなった竹の前に勝斎が正座している。新一郎はすぐにその場を呑み込んだ。以前、師匠が“居合いをやる”と聞いた事がある。その居合いを、今日伝授してくれるのだ。新一郎は胸の高まりを押さえ切れなかった。 折りしも日が西に傾き、蝋燭の炎が夕焼けの空に吸い込まれるかの如く時々チリリリとゆらめき、かすかな音を立てる他は、風の流れも止まっているかの様な静寂さであった。 糸が燃えて切れた。“ピッ”という音がしたようでもあったし、空気の破れる気配であったのかも知れない。一瞬白刀がきらめいて、竹が真二に斬られた。その時、既に刀は鞘に納まって、元の静寂に戻っていた。勝斎は矢張り微動だにせず黙想のままである。 「勝機は鞘の中じゃ。音を斬る。良いか、精進せい」 とだけ言った。新一郎十七才の時である。それから四年、新一郎がその居合いを会得した時、勝斎は他界していた。“剣の時代は終わる”と考えた新一郎は、家を継ぐ気になった。 「跡目を継ぐのなら断然蘭学でやる。漢方では駄目だ。『臓志』を見ろ。『解体新書』を見ろ。今から百年も前なのに、あの図版と漢方医学は比較にならぬ。漢方など医学ではない」 そう思って江戸を後にした。しかし今、なまじ習った剣で、新一郎の運命が狂おうとしている。新一郎は思わず皮肉ともつかぬ笑いを浮かべていた。 《その二》 作:柳田 通(医学部Ⅲ年) 絵:山口恵子( 看Ⅱ年 )  1 (三) 入隊 部屋に入ってきたのが沖田であると分かるや、新一郎はそれまであった緊張感が急にほぐれて行く様な気がした。年令の近さも手伝ったのであろう。この時沖田総司二十才、新一郎二十一才である。 「いや、そのまま、そのまま樂にして下さい。所で、お手前、人を斬られたのは今回が初めてとお見受けしたのですが」 「はあ、未熟のなせる業、峰打ちも考えずに斬ってしまい、申し訳ない事と思っています。して、あの方はいかがなりましたか」 「橋だ君ですか。正直言って気の毒でしたが、お手前には責任のないこと、その心配は御無用にござる」 と言うことから、京の実情や江戸の話、道中行の事など話が飛んだ。新一郎は、沖田が人なつっこいのについつい誘われた。それは剣の技と同様、沖田の天性であった。界隈の子供もすぐなつき、沖田が一緒に遊んでいる風景は、とても新選組隊士とは思えない。 「藤枝殿、実はこれは内密にして頂きたいのだが、話しても宜しいかな。もし、貴殿の意に沿わぬ時は聞き流して下さい」 「私で差し支えなければ」 と、言ってしまった。引き返しがつかなくなった。 「実は、今隊内に独断専行を押し進める部分があって、これをこのまま放置すれば新選組の存亡に関わってくるかも知れないのです」 「すると、これに私を」 と、新一郎は人を斬る仕草をした。 「貴殿の腕を見込んで」 「・・・・・」 新一郎は思わず腕組みをして考え込んでしまった。初めて会った者にこれ程の大事をうち明けるのだから、あの居合いが沖田らに随分見込まれたのであろう。それだけなら新一郎も満足感で済んだ。だが、その為に自分が血なまぐさい泥沼に引きずり込まれるのは御免こうむりたかった。それは自分の性には合いそうもない。それに、話を聞いたからといって隊に入らねばならぬ義理は少しもないし、それは沖田も承知している。しかし、新一郎は、内部抗争のある組織がどういう結末になって行くのかという事への興味、好奇心が湧いた。蘭学という決められた一つの道へだどり着く前に、回り道をするるのも良かろう。今しか出来ない事だ。それに、あどけない中にもどことなく憂いをたたずませた白い透き通った顔の沖田をもう少し知ってみたいと思った。 (四) 反目 勤王派の暗殺騒ぎは文久二、三年に至っていよいよ激しくなり、新選組の果たす役割もいきおい大きくなっていた。しかし、この時隊は三頭政治という形であった。つまり、局長に芹沢・新見・近藤、副長は土方と山南、その下に助勤、監察と続く。これでは隊の運営のうまく行く筈がなかった。隊創立当時からこれを知っていた土方は、いずれ機の熟するのを待って近藤擁立を謀ろうと考えていた。これを決定的にしたのが大和屋事件である。文久三年七月、天誅組が軍資金調達を豪商に掛け合って断られた為、先ず八幡屋卯三郎の首を三条大橋にさらした。その首の横に高札を立て、《大和屋、丁子屋、布屋も同罪だから天誅を加える》と恐喝したので、三人青くなった。すぐさま軍資金を献上して首をつないだ。 所がこれを芹沢がしったから堪らない。 「賊にくれる金があって、我々には雀の涙程の献金しか出来ぬなど言語道断、新選組の怖さを思い知らせてやる」 とばかりに、隊員を引き連れ、大和屋に隊費借用を強談判した。これを番頭が断ったので、芹沢はますます激高した。日頃芹沢に何やかと意見がましき事を言う近藤、土方が留守なのを良い事に、夜になると大砲を持ち出して大和屋を包囲し、さかんに撃ち込んだ。それでも足りずに、家に火を放った。さすがの大和屋も青くなったが、事ここに至っては為す術もない。兎に角奉行所へ届け出た。町火消しや所司代の火消し役が出動してきたが、近くの屋根上で高見の見物としゃれ込んでいた芹沢は、 「火消しは無用、鉄砲で追い返せい」 と、隊士に行く手をはばませた。大和屋は灰燼と化した。 新選組の生みの親守護職会津侯も、さすがにこの蛮行を見かねた。その数日後、近藤、土方が守護職に呼び出された。芹沢の処分である。 (五) 詰腹 文久三年九月八日、丁度新一郎が京都に着く二日前に、局長の新見が腹を切らされた。新見が愛妾と酒を酌み交わしている所へ、近藤、土方らが押しかけ、新見の隊規違反の数々を上げて切腹をせまったのである。新見もいさぎ良かった。ねばり抜けば、芹沢の計らいで命も延びたであろう。しかし、この事を一番良く知っている土方は、ここでどうしても新見を片付けて置く必要があった。もし新見が拒否すれば、その無腰の首を撥ねるつもりであった。新見は芹沢の行く末をぼんやりと考えた。が、もはやこれまでと観念するや、脇差しをおもむろに抜き放ち、左腹部にぶすりと突き立て、一気に横一文字に右へとかき斬った。 当時の切腹の作法は既に形式化されていた。腹の表皮を薄く傷つけ介錯を待つのである。腹に小刀を深く突き立てると、痛覚の反射で背筋が収縮しのけぞってしまい、介錯人の手元が狂う。こうなると、切腹は修羅場と化し悲惨である。新見はそれでも脇差しを深く突き立てていた。酒の酔いが手伝っていたのかも知れない。姿勢の乱れはなかった。傷口が開いて内臓が飛び出した時、新見の首は切り落とされていた。 芹沢が急遽駆け付けたのは、それから半時も経っていたであろう。当然自派の新見が詰め腹を切らされたのだから、芹沢の怒りはすさまじかったが、もはや後の祭りである。近藤等に、 「用意周到な事でござるな」 とだけ、不気味な捨てぜりふ吐きかけた。土方は寒気を感じた。 「早く始末せねば」 近藤も土方もそう思った。 《その三》 作:柳田 通(医学部Ⅲ年) 絵:山口恵子(看学Ⅱ年)  (六) 芹沢鴨 九月十八日は残暑も厳しく下弦の月が大きな傘を付けてぼんやりと地上を照らしていた。土方が飲みながら、いらいらしていた。決行日は今夜だというのに、この明るさでは拙いと思った。そんな土方の気持ちを察っしてか、五つ(八時)を過ぎた頃、にわかに厚い雲が空を覆い、月の光をさえぎった。酒宴いよいよ盛りとなる頃、一つ二つと大粒の雨が落ち、たちまち土砂降りの雨となった。土方が小躍りしたのは言うまでもない。芹沢にとっては悲運であった。酒宴も明け、芹沢は例の如く大酔して、駕籠で八木屋敷の住居に戻った。そこにはお梅が待っていた。別間には腹心の平山五郎と平間重助が、既に一足早く帰って寝ている筈であった。二人にはいずれも女がいる。芹沢を始め二人してこうであったから、隊内の綱紀は相当緩んでいた。芹沢の暗殺の後、隊内の規律は相当に厳しくなって行く。まさしく、芹沢のいた頃を知る平隊士達にとっては、 『もとのにごりの田沼恋しき』という嘆きとなってくるのも当然である。 芹沢はずぶ濡れになった着物を脱ぎ捨て、素裸になると水を三、四杯頭からかけて泥を取り、お梅に拭かせるとそのまま布団に入り込んだ。雨は相変わらず滝のように降っている。とは言うものの、一向に残暑はおさまらず、建具は開け放しにして置いた。芹沢も豪放で恐れられていたから勤王浪人が部屋に踏み込む等は夢にも考えなかったに違いない。まして、自分の隊の者が侵入する筈がなかった。それに、平山、平間は使い手である。 九つを過ぎた頃、沖田ら五人の黒い影が八木邸に忍び込んだ。蚊遣りの香のにおいが鼻をつく。芹沢は既に寝入ってしまい、高いびきをかいていた。山南らは先ず芹沢に集中攻撃を掛ける事にした。芹沢を打ち損じたら、それこそ取り返しがつかなくなるからだ。五人とも間取りは十分検分済みでどこに何があるか、すっかり呑み込んでいた。山南の合図とともに素早く部屋に入るや、五本の刀が二つの影をめがけて音もなく突き立てられた。お梅は胸と腹を刺されて声も立てずに即死、巻き添えを食ったお梅は哀れであった。闇目にもその白い裸体がくっきりと浮かび上がり、新一郎はじめ皆ドキッとした。芹沢は、 「お、おのれ、闇討ちとは・・・」と叫ぶと、腹に刺さった刀を払おうともせず、そのまま起き上がり、床の間の刀掛けの大刀に手を伸ばした。その手をすかさず切り落としたのは沖田である。沖田は暗闇の中にも平然として平然としており、新一郎が思うに、あのあどけない沖田の表情は少しも変わっていない筈であった。 裸身の芹沢がなます切りにされて絶命する頃、ようやく騒ぎに気付いた平山が急ぎ浴衣一枚を羽織って、 「何者だ」と芹沢の部屋に駆け込んだ。その刹那、新一郎の刀がその首を一気に切り落とした。土方のもくろみが当たった。暗闇と言う事が、新一郎に血の恐怖を取り払う事になり、新一郎をして躊躇なく刀を走らせる事になった。 平間の方は機転のきく男だったようである。 「命あってのものだねじゃ。逃げよう」と、着物を小脇に抱え愛妾糸里と手を携えて雨中に姿を消した。平山の女・小栄もうまく闇の中を逃げのびた。部屋が芹沢の所から離れていたのと、賊が芹沢に手一杯で女には関わりあっていられない事が二人の女性に幸いしたのであろう。平山も手向かわずに逃げれば、命は助かっていたはずである。山南らは、芹沢を始末した事を見届けると、新一郎に、 「芹沢に天誅を加えたり」と怒鳴らせた。新一郎は新入りだし、その声を八木家の人に知られていなかった。 ようやく騒ぎに気付き始めた八木家の人々が、事の重大さに驚き、いくばかりも離れていない近藤、土方の宿泊している前川邸へ急報に走った。近藤、土方ら隊士が、 「賊はどこだ」とおっとり刀で現場に駆け付けた時、芹沢、お梅、平山の三名が見るも無惨な姿を横たえていた。平山の首は数歩体から離れて転がっていた。現場には賊の遺留品らしき物は何一つなく、日頃芹沢に恨みを持つ者が勤王方ばかりである事から、その仕業であろうという事になった。この時、暗闇の中で近藤、土方の両名がどのような顔をしていたかは、もはや想像に難くない。すぐさまその場で両人の死体は白布に捲かれ、紋付きの正装がなされた。犯人不明という事で、外部へは『急病頓死』とだけ発表した。 九月二十日、壬生の前川邸では芹沢の葬儀が盛大に執り行われた。この日は残暑が相も変わらず厳しい中にも、昨夜とは打って変わって空は冴え渡り、すがすがしい青空が葬儀に来る人の目にまぶしく映った。この時の近藤の弔辞は見事であった。 「・・・ここに至って新選組も隊士四十三名にも達し、隊の本分を発揮出来るのはいよいよこれからであると言う時に、勤王浪士の凶刃に倒れられた芹沢局長の心にあまりある無念の心府が、いかばかりであったかと思うと、我々一同断腸の念の思いの込み上げてくるのを押さえ切れません」と、その声は涙にむせて肩うち振るわせて込み上げる慟哭に、弔辞の弁も度々途切れ、式場のあちこちからすすり泣きの声が漏れた。副長の土方は、剣のみに生きて来た近藤がここまで役者上手である事に胸をなで下ろし、新選組の新しい門出に万感の思いを走らせた。 一方、新一郎は末席でさいぜんから、もうもうと立ち上がる線香の青い煙をじっと見つめていた。それは天上に届く前に跡形もなく消え去っていく。しかし、消え去るその下からは次から次へと新しい煙が湧いてくる。 「この煙は一体俺に何をかたりかけようとしているのだろうか」、それだけを漠然と考えていた。そして、人間の知られざる裏側をかいま見て、空恐ろしさのわいてくるのを感じていた。 (その四) 作:柳田 通(医学部Ⅲ年) 絵:山口恵子(看学Ⅱ年) 閑話休題:途中で水を差して大変申し訳ない事ですが、《独り言》を書かせて下さい。 私が学生時分の頃、この短文を書く気になった理由は、(その四)以降の話に意を込めた色々の事があったからなのです。当時荒れ狂った学生運動、その様な中でしばし私の心の潤いをもたらしてくれた人、実は、この(その四)以降の文章こそ、私の一番書きたかった所なのです。新選組の挿話は、その入り口に過ぎなかったのです。人命を救う為に旅立った新一郎が、ふとした運命から新選組に入隊し、人を切らねばならなくなった矛盾、新一郎の京でのおそのとの出会い、その新一郎の心の葛藤・悲哀を、おそのがどのように思い励まし、人の道に導いて行こうとするかを切々と書ければ良いと思っていました。ですから、12回連載で1年間位は掛かるだろうと考えていました。 この文中のおそのは《京都女》です。私は『京言葉』の響きの美しさにあこがれ、《京都女》にあこがれを持った事がありますが、《京都女》の事や『京言葉』がまるで分かりません。関東人の聞きかじりで、《京都女》、『京言葉』を書きましたが、矢張り余りに変でしたので、京都出身だった後輩・柔道部の任君に訂正して貰いました。関東人の考えもつかぬ本物の『京言葉』に修正して貰った時には、さすが《京都人》だと感心したものです。所が、当時の大学新聞部の執行部から、 「一人の学友の投稿に、これだけの長期連載を載せた前例がない。そろそろ終章にして欲しい」と申し渡されてしまいました。その後、何年も経ってから、或る高名な劇団演出家に、生意気にもこの文章を読んで頂く機会がありました。すると、すぐに読後の返事が来まして、 「まあ、学生としては仕方のない文章だろうが、何か結末が尻切れトンボみたいに急遽終わっている感じだ」と指摘され、 「さすが脚本家、演出家だな。文章に対する洞察力が何ともすごい」と思いました事を、いまだにハッキリと覚えています。その時、文章を書く恐ろしさ・難しさを知って、私は生意気にも考えていた文筆家への道を断念する事にしたものです。 昨年(2004年)、10代の2名の女性が、由緒ある《芥川・直木賞》を受賞しました事は、この分章をお読み下さった方達もご記憶と思います。私も、樋口一葉ではありませんが、10代の女性が本を書いて、《芥川・直木賞》を受賞するなんて、何てすごい事だろうと思いました。一方で、そのタイトルからして受賞に値する小説なのだろうかと疑心暗鬼になったものでした。買って読めば、多分“お金が勿体ない事になるだろうな・・・”と思いながらも、その受賞作2冊を購入して読んでみました。案の定、読後、本を見るのも厭で処分してしまいましたが、『背中を蹴りたい・・・』の本の冒頭の言葉、『寂しさが鳴る』との下りで、もう本の先行きが読めた気がしたものです。尤も、逆に『寂しさが鳴る』と言う発想が、いかにも“10代の女性の奇想天外な感性”らしいとの事で受賞したのでしょうか。《芥川・直木賞》も地に落ちたな・・・》、と失礼ながら思ったものでした。 2人の受賞作の分章は、もう読むに耐えないミー・ハー族が日々思い付いた言葉を羅列した内容に思えて、それでも、我慢して最後まで読み通しましたが、読後のあと味の悪さは如何ともし難い感じでした。その後の2人の作家の消息はどうなっているのでしょうか。小説家として益々腕をみがいているのか、私も勉強不足で皆目分かりません。 今年も《芥川・直木賞》が阿倍、角田さんと決定したようですが、受賞作家・阿部さんの談話に、『辞書に載っていない猥雑な言葉と、辞書にしか載っていない言葉を集めて、いびつな分章を書きたい。この自分の試みが読者に理解されるまでしつこく書き続ける』、との新聞記事を読んで、今年は両者の本を買う気にならなくなってしまいました。 本を書くに当たっての最低限の必要事項は、読んでくれる相手に少なからずのわずかな感銘でも得られる様に、『綴り方』位は最低限学んで書く可きであろう、と私は考えます。昨年の《芥川・直木賞》受賞10代の作家の文体は、“文法など意に介さない”とでも言う様な、まるで自分本位の滅茶苦茶な文体です。大体、人生経験の全く少ない人間が、一体何を以って人を感銘させ得る様な事が書けるでしょうか。雨水の注ぎ込まない泉がすぐに枯れる様に、あの様な若者の投げやりでお粗末な文筆家スタイルが、いつまでも続く筈がないと考えますが如何でしょうか。あの高名な太宰治だって、文筆構想に行き詰まって、最後は入水自殺までしているのです。 それにしましても、当時学生で何も知らなかった私が、能くもこの様な文章を書けたものだと今になって驚いています。私の心の中に熱いものがあったからでしょう。 転写しながらも、当時の文体の稚拙さが恥ずかしくなり、四回以降は原文に忠実な事をかなぐり捨てて、毎回幾らか本の少し訂正に至りました。幾ら納得したつもりでも、これで完成と言えない所が辛い感じです。何度読んでも、必ず訂正したい箇所が出てくるのです。芸術家も、最後まで納得出来ずに何度も何度も手入れをしているとの話を思い浮かべます。 この様な事を今日(2005.3.1)ふと思ってしまいました。  (七) つた屋 京都東山の麓は祇園である。その一角の水茶屋《つた屋》に、新一郎はおそのを膝元にどこを見るともなく夜の草花に目をやっていた。 近藤、土方を筆頭にした新選組では、しばらくの間は芹沢派の粛正が続き、隊内は血の臭いに満ちていた。無論、外では不穏な浪士を見つけ次第斬殺するか捕縛している。また、隊内では、隊士の切腹には新参者が度胸を付ける為にと介錯を命じられ、新一郎はその様な光景を目にする毎に身のつまされる思いがした。それにも増して、市中見廻りの末に刀を抜かねばならない仕事には、人命を助けるべき医師を目指す自分からすれば実に不合理な事に思われ、いても立ってもおられぬ思いであった。 その様な新一郎の毎日に、ほのかな安らぎをもたらしたのがおそのである。新一郎はおそのとの出会いをぼんやりと考えていた。 (八) おその 「そんなしけた顔をしていず、酒でもあおってきな」 と橋本に言われ、ふと行く気になったのは、新一郎にとってそれが一つの救いになるような気がしたからである。つた屋の小部屋に上がった新一郎は、しばらくの間一人で飲んでいた。その内手が空いたのか、女中が入ってきた。それがおそのである。 「俺は女など呼びはせんぞ」 とつい野暮な事を言った。 「そやかて、うちの方はお勤めどすから。あのう、お侍さんは壬生のお方やおへんか」 「うっ? 何故だ?」 「何やよう言えまへんが、血のにおいが・・・」 新一郎は、そこまでどっぷりと新選組のにおいが染み込んだかと思うと、ぞっとした。 「そうか、血の臭いか・・・」 「ちごうとりましたら堪忍どすえ」 「いや構わぬ。お前の言う通りじゃ」 「うふ、血の臭いは嘘どす。壬生の方が時折来られますよって、お侍さんも何となく分かりました」 「もうここに長いのか」 「いえ、まだ一年位です。やっと慣れましたが、まだまだつろう事が多おす」 とおそのは言ってしまった。つい、つた屋の娘と言うのがためらわれたのである。 「辛いのは俺と同じだな」 「あら、お侍さんも・・・。でも、そやから、こういう所にお出なはるのやろ」 「お侍さんはよしてくれ。俺は藤枝と言う」 「うち、おそのどす。よろしう」 「おそのか。良い名前だな。目が綺麗だ」 「あらっ、お上手どすこと」 「いや、本当だ。京は美人が多いと聞いていたが、こうして近くで見るとなる程・・・」 「うふ、どなたはんもそう言わはります。そして、その後口説かれますよって、油断なりまへん」 「さすが俺の手の内を読んでいる。あははは・・・・でも、綺麗なのは綺麗だと言うさ」「へえ、おおきに。お言葉だけもろうときます」 それから、新一郎は暇を見つけてはつた屋に通った。おそのと軽口を叩いている時、新一郎は何も彼も忘れて二人だけの世界に没頭出来た。 おそのは美人ではあったが、所詮艶を感じさせるにはまだあどけなく、おそのが余りにも水商売と場違いでかけはなれているのに、最初はとまどいながらも、だからこそおそのと一緒にいると心が洗われる様な安らぎを覚えていた。新一郎がおそのはつた屋の娘であると知ったのは、おそのを女にした時であった。新一郎が最初に出向いた日、つた屋では人手が足りなくて、つい娘のおそのを出したのである。 (九) 夜風 あれは新一郎が酒をあびる程飲んでつた屋にやって来た日であった。その日、市中で浪士を一人切った新一郎は、飲まずにおれなかったのである。 「どうされたんどす?」 「何でもない。何でもない。お前なんかに俺の気持ちが分かって堪るか」 「別にうちは分かろうと思うとりまへん。そやかて、こんなに飲まんかて・・・。そら、うちなんか藤枝様から見ればやや子みたいやけど、でも、うちかていつまでも子供やおへん。こんなに心配しとりますのに」 新一郎はその様なおそのの言葉も耳に入らず、胃の中の物を皆吐き出してうめいていた。吐き終わって、おそのの持って来た冷めた番茶をすすると、ようやくいつもの自分に返ったが、頭の方はくらくらしていた。 「夜風にでも吹かれてくるか」 と言い置くと、ぶらりと外へ出た。凍て付くような星が三つ四つ輝いていた。四条大橋を過ぎると、もう野原が続く。ススキが穂先をゆらゆらさせ、虫の音さえ、更けゆく秋を思わせていた。 「どうして付いてくる?」 「心配どすもの」 「俺の方は一向に平気だ。お前の方こそ怖かろう」 「ちっとも。藤枝様を信じとります」 「信じる? 何を? 今の俺は何をするか分からないぞ」 「そんな事あらしません」 「あっ、蛇だ」 「きゃっ」 とおそのは新一郎にしがみついてきた。 「それみろ。蛇なんかこんな夕暮れにはでないのだ」 「いやっ。うちを騙したりして」 と、その時パサッと羽音がした。ねぐらについていた小雀が、二人の足音に驚いて飛び立ったのである。新一郎は、おそのが叫んで新一郎にしがみつかない内に、もう反射的に刀の柄に手を掛けていた。おそのは夢中で新一郎にしがみついている。 「大丈夫だ。鳥だよ」 そう言って、おそのの手を振りほどこうとして、おそのの方をじっと見た。かすかに震えているおそのの手が余りに冷たいのに新一郎は驚いた。 「寒いのか? 手が冷たい」 「それは反対どす。心があたたかいから手が冷うなるのおす」 「心があたたかいか・・・。おそのさん、人斬りの俺は嫌いか?」 「・・・」 「嫌いでも構わぬ。俺は、今このままお前を抱きしめたい」 「先程から何をお考えどすか」 「うん?」 「いや、わろうたりして。うちにも聞かせて」 「お前を抱いた日の事だ」 「まあ、いやっ」 庭の草花に長い影が落ちるようになっていた。 (その五、終章) 作:柳田 通(医学部Ⅲ年) 絵:山口恵子(看学Ⅱ年) (十) 初心 新一郎はおそのに出会う以前、それとなく沖田に言った事がある。 「沖田さん、俺もそろそろ身の振り方を決めねばなるまいと思うのだが・・・。何か最近隊は俺にふさわしくない様な気がして」 「そうだろうな。医者を目指す者が人を斬っているのだから。だが、もうしばらく待ってくれ。隊は今が一番大切な時だ。新しい統制の下に・・・」 「その統制の下に、何人もの人が毎日死んで行く」 「それは言わないでくれ。百も承知だ。しかし、京の治安は守らねばならぬ」 「その為に人を斬り、京の都の町民から新選組は鬼の様に恐れられている」 「そうだな。が、今、京の都を守れるのは我々だけだ。その内分かってくれるだろう」 「沖田さんは羨ましいな。楽天的で何も心配事がないようで。そう言えば、『沖田さんは剣は強いのに、まるで遊びを知らないガキだ』なんて言っている人がいましたが」 「あははは・・・。俺の好きな人は姉上一人で充分さ」 新選組から抜けるのがしばらく困難と知って気落ちしていた新一郎は、それでも今度こそおそのの為にも長崎へ行こうと思った。江戸の親元からも時々心配の便りが来ていた。いざと言う時は、沖田が自分を助けてくれる。大体そもそもの始まりは、沖田が新一郎に頭を下げて頼んで来た事なのである。その責任は沖田が取って当然の様に思われた。 (十一) 私情 おそのの所に一晩泊まった翌日、隊に出動命令がかかった。新一郎は、 「またか・・・」 と厭な気分が先走った。 「人を斬らずに済めば良いが・・・」 その考えは、もう新選組を脱退したに等しいものであった。新選組という一隊となって行動する時、私情は許されない。 しかし、この時新一郎が人を斬りたくないと思ったのは、おそのに、 「あの・・・、やや子が出来おした」と言われたからであった。新一郎は、新たに芽生えた生命に、深い感動を覚えた。 「おその、一緒になろう。二人でやっていこう」 「嬉しうおす。新一郎様」 そして、燃えるような一夜を過ごした次の朝、二人の感銘をそっと閑かにして置きたいと思っていた。 だから、浪士が(とは言っても、逆の見方では維新の革命の戦士であるが)抜刀して新一郎の方に向かって突進して来た時、新一郎は刀の柄に手を掛けたものの、身を交わしてとうとう抜刀はしないでしまった。 「藤枝君、何故斬らなかった」 と田中が叫んだ。この時、言い訳なら何とでも言えたが新一郎は黙ってしまった。例え何を言おうとも、新一郎の新しい生命へのあの感銘をとうてい人には分かってもらえるものではない。分かるとしたら、おそのしかいない。 新一郎のこの失態は、当然新一郎の属する五番隊長武田観柳斎の耳に入った。武田は眉をひそめた。新一郎は、今が長崎へ行く潮時だと思った。 「おそのも連れて行こう。そうして長崎で蘭学を勉強するんだ。新選組に居た事は忘却の彼方に押し流し、それまで人を斬ったわびの為にも、何人もの人を助けよう。もう、回り道はお終いだ・・・」  (十二) 沖田総司 「沖田さん、かねがね思っていた長崎行きの事だが、そろそろ俺も隊の引き時だと思うので、土方さんにその旨伝えて貰えないだろうか?」 「そうか。矢張り長崎に行くか」 「済みません。隊は私にどうも合わないのです」 「そうだな。俺が引き留めたのがいけなかった」 「いや、私もあの時は自分の進む道に踏ん切りが付いていなかったものですから」 「分かった。伝えよう」 それから二日程経った十八日の晩、 「藤枝君、許しが出そうだ。今夜は前祝いに二人で飲みに行こう」 と沖田に声を掛けられ、新一郎は余りに急な事で一瞬我を忘れた。 清水に近い小料理屋桐壺は、沖田も馴染みらしく、女将の歓待もあって、新一郎はついつい深酒をした。深酒をしながら、新一郎は、一瞬だが何気なくふと芹沢鴨の事を思った。沖田は、まるで何事もない様な顔付きで新一郎に酒を注ぎながら、 「二、三日の内に許しが出るだろうから、ゆっくり身体を休めて旅の用意でもする様に」 と、あれこれいたわってくれた。 「沖田さん、いつも我が儘ばかり言って申し訳ありません」 「そんな事、気にするな。それより、藤枝君にはいい人が出来たと言う噂だが・・・」 「いやあ、そんな事まで御存知でしたか」 「ああ、地獄耳だ。君が羨ましい。俺など何の為に生きているのか分からない」 沖田が咳き込んだ。新一郎は、“おやっ?”と思った。 「沖田さん、その様な咳をよくするんですか?」 「ああ、でも時々だ。そう言えば、藤枝君は医者の卵だったな」 「いや、まだ卵にもなっていませんよ。これからです」 「・・・」 沖田はこの時、何か言いかけたが黙ってしまった。 (十四) 抜き討ち 小料理屋からの帰り道、二人は肩を並べて和気藹々に話をしながら歩いた。下弦の月が夜空に冴え渡っていた。それは氷のように冷たく、来たる可き冬が例年になく寒くなる前兆の様であった。 つと、沖田が立ち止まった。 「おやっ?」 と思って後ろを振り向こうとした新一郎の背中に、抜き打ちざまの沖田の大刀がななめ一文字に切り下ろされていた。その間合いのすさまじさは、居合いの新一郎とて刀を抜くいとまもなかった。新一郎は、瞬間おそのの事を思った。 「おその・・・」 と叫んだが、それは声にならなかった。沖田は、組織の冷酷さを厭と言う程思い知らされ、大粒の涙を幾滴も落としながら刀の血潮をぬぐおうともせず、月明かりの道をひたすら鬼気迫る勢いで壬生に向かって歩いていた。 元治元年六月五日の池田屋事変で、新選組はその名を天下にとどろかしめた。その時、おそのはまだ子供を胎内にい抱いていた。生まれるまでに、もう幾ばかりもない頃であった。 《後書き》 仕事の合間に、文章を書き写してホームページに載せる事は結構大変な作業でした。NHKの『新選組』が放映されている内にと思っていましたが、『新選組』も遠の昔に終了してしまい、今は『源義経』の番です。月日の経つのは本当に早いものです。生けるものは、いつの日にか必ず黄泉の国に旅立たねばなりません。 この文中に出て来た《おその》さんも、それから23年後に42才の若さで病没・鬼籍に入ってしまいました。鬼籍に入った事など何も知らないでいた黄泉の国の新一郎が、奇しくも《おその》に逢える日が来た事を知るや、腰を抜かさんばかりに驚愕してしまって、かなりしばらくの間一人号泣していた。 |
